仕事
今年はデザイン業もといファシリテーション業が多くなった。企画MTGをしながら全職種で集まってその場でFigmaで画面を書き起こしていくことがとても多くて、なかなかしんどいが楽しかった。見た目を書き起こしながらのファシリテーションはデザイナ側が楽で良い。会社からipadが支給されたので、ペンでその場ですぐ絵を書いて出すということもできるようになってとてもやりやすく感じた。 一方コードをあまり書かなくなったのでとても焦りを感じた。どんどんやり方や勘所を忘れていってしまう… 所詮私は書き方を覚えていただけで、そんなに深く何かわかっていたわけではないというのを痛感せざる得ない。残念….。
それからまた今年も周りの人に恵まれていたな〜と感じることが多かった。この人のここが素敵だな〜と思うことがたくさんあった、自分に取り込んでいきたい。
子供
甥っ子が産まれて本当に可愛い。ずっと地元を離れていたが、今年は甥っ子見たさに帰省することが多くて、両親も甥っ子がいることで張り合いが出てイキイキとしていた。今両親が健康でいてくれることがどんなにありがたいことか。家族の良さを再確認した年でもあった。 そして私も今年ようやく子供を授かることができた。お腹の中で動いている時のこの愛おしさ。子供ができた時の喜び・・!こんなに嬉しいことだなんて・・!! 心拍の音を初めて聞いた時、手足が生えて動いていた時、ああ、、この子の人生はもう始まっているんだ…と感慨深い気持ちになってたまらなかった。
それから、全国どこからでも仕事OKになったので、出産を期に夫の地元で暮らすことにした。東京よりも友達が多いし、思い出の場所も多くて東海が大好きなので、本当に楽しみ!行きたいこともしたいこともいっぱいある。かといって完全に東京から離れてしまうのも少し寂しい。感覚が鈍くなってしまいそうな怖さがあって、行きたい時は出社してOKなのもとても助かる。たまに東京に行きたい。
デッサン
今年は土日せっせとデッサン教室に通った。会社から補助も出るし、真剣に取り組んだ。 もうだいぶ鉛筆には慣れて、艶感のコントロールや、黒の彩度で遠近感を出すことも自由にできるようになった。今年描いた中では、鳥の剥製のデッサンが特に楽しかった。 模刻でアクリル着彩ができたのもよかったな。自然物の色を再現するのがほんと面白くて、どんだけ見ていても飽きない。最高だな〜。絵を評価するときの語彙もだいぶ溜まってきた。先生との会話が結構大事で、どんな表現をどんな言葉で伝えようとしていて、それがどんな技術でできているか分解して自分の中にストックしていく感じ。これは隣で描いてくれたり細かい指導をしてもらえないと得られないのでとてもありがたい。 今の教室が本当に好きなので、できたら続けていきたいけど、来年はどうなるかな..。
放送大学
3年目。多分しばらくやめなさそうなので全科履修生で入学することにした。 今年は西洋音楽史、日本政治思想史、近現代ヨーロッパの歴史、フィールドワークと民族誌の4つを履修。特によかったのは日本政治思想史で、先生の著書「滝山コミューン一九七四」がきっかけでなんとなくで履修したが、全く知らないことだらけですごく面白かった。江戸まで遡って、鉄道や地理的なこと、思想よりもっと大枠の話だったので入りやすい。先生の他の本も読まねば…。 他は、人間にとって貧困とは何か、現代の国際政治、国際理解のためには休み中に講義を聞いたりしていた。ウクライナの戦争が始まった辺りで高橋先生の授業が話題になっていたので一通り。先生の授業もすごく面白かった、もう退職されてしまうのがとても悲しい。 ところで世界文学や西洋音楽史を受講していて薄々気づいて目を逸らしていたのだが、私は近代史の知識がなさすぎる。もうこれは克服しないと何も楽しめないし何も考えられない…と思って今履修中。もうすぐテストだけど仕上がりはイマイチ。。
読んだ本
突然テッドチャンが良いことに気づいた。大好き...。
松陰美術館の館内公開に行って。この美術館めちゃくちゃ好きだな。良い建築。
仕事関係はこの辺。everylayoutはチームで輪読会をしたりした。
世界文学への招待(旧)から。ほんとはもっと読むつもりだったのに全然積読消費できてない
今年は珍しく漫画も少し読んだ。
その他
ゲーム
アウターワイルドのDLCをやって、その後アウターワイルドゾンビになっていた時期があった。
界隈では有名な2人のよう。これを見ると初回プレーの興奮を味わえてかなりいいです。
相変わらず一番プレーしていたゲームはリングフィットでした(82h)。 just dance 2022を買ってからは毎日30分ほど踊るようにしててこれで運動不足を解消していた。 とっても不恰好だけどそんなの関係ない。踊るとストレス発散になって良い〜。
記念日
結婚記念日と新婚旅行記念日に美味しいものを食べにいくというのを初めた(34になって今さら!) 結婚記念日は割烹を。新婚旅行記念日はモロッコ料理を。(モロッコだったので) なんかすごく特別ってわけでもないけど、夫婦で食べに行けるのって楽しいなぁ。 今年付き合って10年経ったけれど、ずっと変わらず楽しい日々を過ごせていて夫にはほんとに感謝している。
この記事がとても良くて、ブラウザのタブを開きっぱなしにしてたまに読んでいる。 この中の「あなたは、そのままでいいんです」の項目はうなづけることが多くて 私も夫に愛されて生かされているのを感じる。だから頑張れる。ありがたいことだ。
音楽
あんまりじっくり聴き込むことがなくなってきたな。 今年聞いていたのはこの辺かな〜。
突然のマッコイタイナーは、たまたま入ったjazz喫茶でかけてて、めちゃくちゃいいじゃん!となったので。




















![Sometimes I Might Be Introvert [解説・歌詞対訳 / 国内盤] (BRC674) Sometimes I Might Be Introvert [解説・歌詞対訳 / 国内盤] (BRC674)](https://m.media-amazon.com/images/I/41YHa38VCTL._SL500_.jpg)
















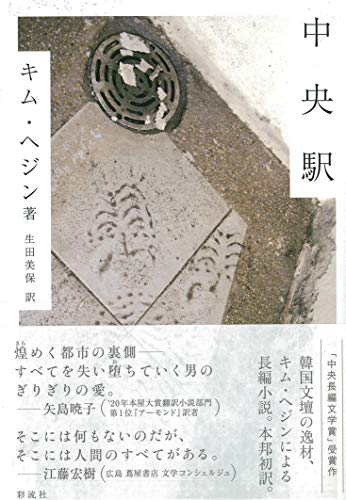





![KiCk i [輸入盤CD] (XL997CD) KiCk i [輸入盤CD] (XL997CD)](https://m.media-amazon.com/images/I/41hT6zIUrOL.jpg)

![Healing Is A Miracle [Analog] Healing Is A Miracle [Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/61YE6b+9XlL.jpg)

![Magic Oneohtrix Point Never [輸入盤CD] (WARPCD318)_1129 Magic Oneohtrix Point Never [輸入盤CD] (WARPCD318)_1129](https://m.media-amazon.com/images/I/613sBOUwYgL.jpg)









